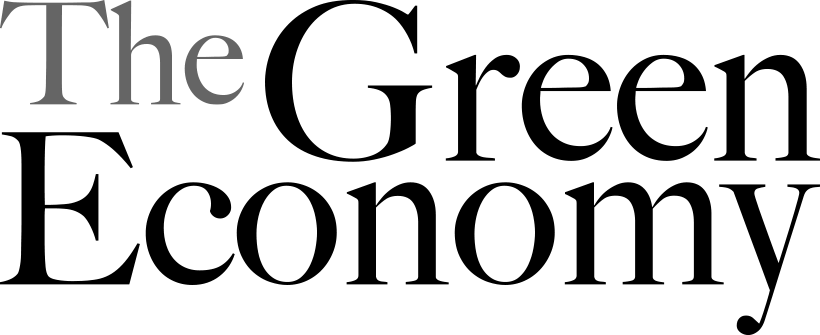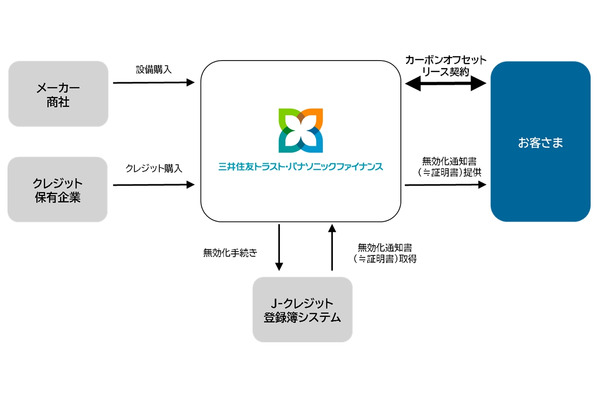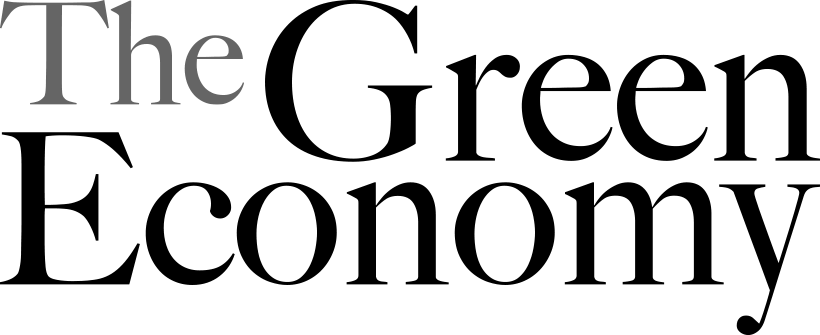アサヒグループホールディングス株式会社の独立研究子会社であるアサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社(AQI)と、SyntheticGestalt株式会社および国立大学法人東京科学大学と、2024年下期からAI技術を活用したPETボトル分解技術「バイオリサイクル」の研究を開始しました。
「バイオリサイクル」は、PET素材を中間原料に戻した上で再重合する新たなPET樹脂を作る方法です。化学的な分解工程を酵素分解に置き換え、生物由来の分解酵素を利用することで、反応温度を大幅に低下させ、常温かつ常圧でリサイクル実施できる特徴があります。従来のPETリサイクル手法と比較して、環境負荷やコスト低減に貢献することを目指しています。
本研究では、AQIがアサヒ飲料などの事業会社から得られる知見を活用し、市場ニーズや事業課題を含めた実用化に向けた評価を行います。SyntheticGestaltは、同社のAI技術を用いて2.5億種類の遺伝子ライブラリーから高機能かつ高付加価値の新しい分解酵素「PETase(ピーイーティーエース)」を探索します。東京科学大学は、分子進化工学の研究で培った実績を活かして実験と評価を担当します。
アサヒグループは、2040年にCO2排出量"ネットゼロ"を目指す「アサヒカーボンゼロ」を設定しており、2030年までに「PETボトルを100%リサイクル素材、バイオ由来の素材等に切り替える」という目標を掲げています。本研究は、目標実現に向けた重要な取り組みです。
3者はすでに、10種類の有望なPETase候補を新規に発見しており、実験で一定の分解機能を持つことを確認しています。今後は東京科学大学の実験チームがこれらの候補の検証を進めていき、酵素の選定と改良によって実用化に向けてさらに革新的な酵素を見つけ出すことが期待されています。3者は2026年までに実証プラントスケールを稼働可能なレベルの活性を持つPETaseの開発を目指して本取り組みを推進する計画です。
本研究は、アサヒグループの環境負荷低減への姿勢を示すとともに、AI技術と生物学の融合による革新的なリサイクル技術の開発を目指す先進的な取り組みとして注目されています。